家屋や建物は、新築した際に「登記」というものを行います。これらを解体して除却すると、今度は「建物滅失登記」という手続きを行い、その建物がなくなったということを公にしなければなりません。これを怠ると、さまざまなデメリットが生じてしまいます。
今回は建物滅失登記について、自分でできるのか、できるとしたら何を準備してどんな手順で行うのか、など詳しく見ていきましょう。
▼この記事を読んだ人はこんな記事も読んでいます。

建物滅失登記とは

建物滅失登記とは、建物を解体した時や火災や災害で失った際に、その事実を公的書類である登記簿上で更新する手続きです。
また、現存していない建物が、登記簿上では存在していると発覚した場合にも必要です。
滅失登記手続きの完了をもって、現地に建物が存在しないことが正式に証明されます。その後は、土地の売買や新しい建物の建設などが可能になります。
建物滅失登記は、不動産登記法第57条により、滅失した建物の所有者か登記名義人が、滅失した日から1カ月以内に建物を管轄する法務局で行わなければなりません。
土地家屋調査士に全ての手続きを委任しても2週間程度の期間は必要ですし、特に自分で申請する場合は早急に行動すべきです。
建物は、新築・増築した際に登記簿を作成し、解体などで焼失した際に建物滅失登記によって閉鎖します。建物滅失登記は、登記簿を正確に保つための必要な手続きなのです。
また、滅失登記が完了した建物は、固定資産税の課税台帳から記録が抹消されるため、翌年1月1日以降の課税対象からは除外されます。もしも課税が翌年も続くようであれば、建物があった市・区役所や町村役場に申し出る必要があります。
出典:不動産登記法|法務省
滅失登記の費用相場

滅失登記の手続きは、自分で行うことも専門家である土地家屋調査士に委任することもできます。
滅失登記の費用の相場は、土地家屋調査士に依頼する場合と自分で行う場合で異なります。
滅失登記には登録免許税がかからないため、自分で行うこともできるのです。費用は建物の大きさに関係なく、1棟単位で算出した手数料です。この他に法務局や必要書類を揃えるための交通費、印鑑証明などの手数料がかかります。
ただし土地調査家屋士に依頼する場合は、付属建物や所有者と申請者の名義が異なるなど、権利関係の複雑さでも変わってきます。
自分で行う場合
自分で建物滅失登記を行う際の費用の相場は、必要書類を揃えるために必要な約1,100円です。
法務局の窓口で申請すると、登記事項証明書(建物の登記簿謄本)600円と、地図等情報450円が必要です。請求を事前にオンラインで行い、窓口で交付を受けるとそれぞれ480円、430円の合計910円になり、費用を低減できます。
費用は収入印紙で支払います。収入印紙は法務局の販売窓口か郵便局で購入しましょう。
土地家屋調査士に依頼する場合
建物滅失登記を土地家屋調査士に依頼した場合の費用の相場は、約50,000円です。
土地家屋調査士は、土地や建物の調査や登記などに関する専門職です。費用は物件により、諸権利が複雑であったり、広い建物であるほど高くなります。土地家屋調査士に依頼する場合の費用とは、官公庁での建物の名義人などの調査業務、書類作成及び申請手数料です。
なお、建物滅失登記は土地家屋調査士だけが対応可能な業務であり、司法書士には依頼できません。
建物滅失登記を自分で行う際に必要なもの7つ
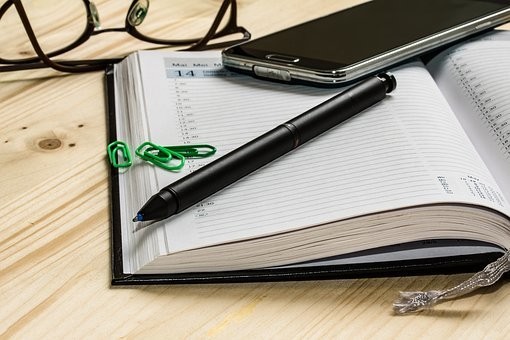
建物滅失登記を自分で行うために必要なものは、ダウンロードできる書類や解体業者が作成する書類など、多くあります。
解体した建物の近くに住んでいても、申請手続きに必要なものをそろえる時間の確保が難しいこともあるでしょう。そういった場合はオンライン申請を活用することで、空いている時間にそろえることができます。
本人が申請できない場合は委任状を、原本還付が必要な場合は原本還付請求書を自分で作成します。
1:建物滅失登記の登記申請書
建物滅失登記の登記申請書は、解体した建物の住所や滅失した理由、所有者を記した書類です。
申請の際、1番上に添付する書類で、確実に準備しなければなりません。建物の種類や構造、床面積や取り壊した日付などを記入するため、取り壊し前に準備しても記載は施工後に行います。
準備する場合は法務局に受け取りに行くか、ホームページからダウンロードしましょう。費用は無料です。
2:該当建物の地図
建物滅失登記に添付する地図は、登記官が現地を確認する際の案内図として作成するため、住宅地図のコピーかGoogleマップが適しています。
住宅地図はなるべく新しい版のものを図書館などで借りましょう。住宅地図またはGoogleマップに該当建物がわかるように印をつけます。
住宅地図は1500分の1または3000分の1の縮尺で作成されているため、Googleマップを使用する場合は縮尺に注意しましょう。
3:現地の写真

建物滅失登記に必須ではありませんが、解体した証明に現地の写真を撮影しておきます。
現地の写真は解体前のものがあると、建物を解体した証明に利用可能です。ただし居住地域が離れている場合などは、無理に用意する必要はありません。
解体した業者が施工証明として工事完了後に添付する場合もあります。業者は地番がわかるように撮影しているため、証明に利用しやすい写真です。自分で撮影していない場合は、活用しましょう。
4:建物滅失証明書
建物滅失証明書とは、解体工事を施工した業者が作成する書類です。
建物滅失証明書は、建物取毀(とりこわし)証明書とも呼ばれます。受け取った際、解体した建物の所在地などの表示及び所有者、取毀の理由、解体した日付と施工業者が記載されていることを確認します。
事前にインターネットなどでテンプレートを基に証明書を作成して、解体業者に押印だけして送り返してもらう方法も有効です。
5:解体業者証明書と印鑑証明書
解体業者証明書と印鑑証明書は、建物滅失証明書とセットで解体業者から発行されます。
建物滅失証明書の工事人を証明するための書類です。建物滅失証明書の印鑑証明書と共に解体工事完了後に受け取ります。
解体業者資格証明書は、「全部事項証明書」や「代表者事項証明書」「現在事項証明書」「現在事項一部証明書」などの名称の書類が発行される場合もあります。建物滅失証明書の工事人欄の記載内容と同じことを確認しましょう。
6:委任状
建物滅失登記を建物所有者が行わない場合は、委任状が必要です。
建物所有者本人が手続きを行う場合は不要ですが、代理人が行う場合は作成します。土地家屋調査士に依頼するとセットで準備します。個人で行う場合はネット上のテンプレートを参考にしましょう。
記載内容は、登記の目的や原因、不動産の表示や指定した代理人の住所と氏名です。原則として実印を使用し、建物所有者の印鑑証明書を添付します。
7:建物の登記事項証明書(登記簿謄本)や図面など
解体した建物の登記事項証明書や図面などは、管轄の法務局で入手可能です。
建物の登記事項証明書は、全部事項証明書を請求します。図面は、地図や土地所在図、地積測量図(筆界特定書)、建物図面及び各階平面図を一括で請求できます。
登記簿では建物の所有者の氏名や住所、抵当権の設定などを確認し、図面では建物の位置関係を、地積測量図では土地の特定を、各階平面図では形状を確認しましょう。
▼この記事を読んだ人はこんな記事も読んでいます。

建物所有者が亡くなっている場合に必要なもの3つ

解体した建物の所有者が亡くなっている場合は、亡くなっていることを証明する公的書類、および申請人が相続人であることの公的書類が必要です。
所有者が亡くなっていることの証明に、所有者の戸籍謄本または除籍謄本を準備します。相続関係書類として、申請者の戸籍謄本と所有者の住民票の除票などが必要です。
遺産分割協議書など遺産に関する書類や法定相続人全員の承諾書類は必要ありませんが、解体前に同意を得ておきます。
1:所有者の戸籍謄本・除籍謄本
家屋の所有者が亡くなっている証明に、戸籍謄本または除籍謄本を準備します。
亡くなった方の配偶者や子どもが同じ戸籍に残っていれば戸籍謄本、戸籍に誰もいない場合は除籍謄本が必要となります。戸籍謄本や除籍謄本は該当する市区町村に出向くか、自治体のホームページに取得方法や必要書類、費用が記載されているため、指定された方法で取り寄せます。
申請費用のほか、申請者の本人確認書類の発行費用が必要になる自治体もあります。
2:申請者の戸籍謄本
建物滅失登記では、申請者が所有者の相続人である証明に申請者の戸籍謄本が必要ですが、亡くなった人の戸籍謄本、または除籍謄本に申請者の記載があれば不要です。
戸籍は夫婦とその子どもで構成され、婚姻などによって除籍して新たな戸籍を作っています。戸籍謄本は戸籍がある市区町村(本籍地)の役所で取得でき、住民票のある自治体ではないため注意しましょう。
所有者の戸籍謄本や除籍謄本と同様の手順で申請します。
3:所有者の住民票の除票または戸籍の附票
建物の所有者が亡くなった際の居住地の証明に、住民票の除票または戸籍の附票を揃えましょう。
所有者の戸籍謄本や除籍謄本に加えて、住民票の除票または戸籍の附票を使って所有者の本人確認を行います。
人が亡くなっても、住民票は除票として記録が残ります。戸籍の附票には、戸籍を作成した時点からの住民票の移り変わりが記録されており、戸籍の附票は戸籍謄本などの取得と同時に申請すると費用と手間を省くことが可能です。
建物滅失登記を自分で行う手順

建物滅失登記を自分で行う場合、解体する建物の管轄である法務局の確認から始めます。
建物滅失登記には、解体する建物の登記の有無を確認します。登記してあれば、登記事項証明書を取得し、建物滅失登記申請書を作成します。書類をそろえて法務局に提出し、登記完了証を受け取ると完了です。
建物滅失登記を申請してから登録完了証の発行まで1週間から10日程度かかります。
1:管轄の法務局の場所を調べる
建物滅失登記は管轄の法務局のみで対応するため、管轄の法務局及びその場所を調べます。
建物の管轄が不明の場合、法務局のホームページの「管轄のご案内」の管轄一覧や地図から都道府県の法務局のサイトにアクセスして調べましょう。都道府県ごとの法務局では、表や地図で管轄する法務局(支局)を確認できます。
それぞれの支局へのアクセス方法や取扱時間も併せて表示されるため、参考にしましょう。
2:登記の有無を確認する
解体した建物の登記の有無を確認する場合は、固定資産税の納税通知書に同封された課税明細書の家屋番号を確認します。
家屋番号とは、登記が完了すると法務局が付与する番号です。家屋番号があれば登記された建物ですが、家屋番号がない場合は未登記の建物の可能性があります。
登記されている建物は滅失登記を行いますが、未登記の場合は申請義務もなくなるため手続きは必要ありません。
3:登記事項証明書を取得する
登記の有無を確認後、必要に応じて管轄の法務局で登記事項証明書(登記簿謄本)、地図等情報など必要書類をまとめて取得します。
事前にオンラインで証明書の交付請求を行って窓口で受け取る場合は「登記ねっと 不動産登記手続」から行います。登記ねっとの受付時間は平日の8時30分~21時までです。
支払いはインターネットバンキングやPay-easy対応のATMで行い、収入印紙は不要です。
出典:登記ねっと│法務省
4:建物滅失登記申請書を作る
建物滅失登記申請書の記載例と建物滅失証明書を参考に作成します。
申請の日付は、法務局に提出する日を記入します。登記事項証明書に記載された不動産番号を記入すると、解体した建物の表示内容を省略可能です。
法務省のサイトからダウンロードしたWord版などは、パソコンで入力してから印刷できます。手書きの場合はコピーを、パソコンで作成した場合は複数枚印刷して、控えも保存します。
5:管轄の法務局へ提出する

書類が準備できたら、建物滅失登記申請書、建物滅失証明書、解体業者証明書と印鑑証明書、建物の地図、現地の写真、建物の登記簿謄本や図面の順番に重ね、左端の上下2カ所をステープラーで綴じます。
委任状を作成した場合は、登記申請書のあとに入れます。書類は2部作成し、解体業者から受け取った書類は返還を求められる場合もあるため、コピーを使用しましょう。
作成した登記滅失申請書は管轄の法務局の窓口に提出します。
6:登記完了証を受け取る
提出後は修正の連絡があれば対応し、その後法務局へ行って登記完了証を受け取ります。
申請した際、窓口に修正日が表示されています。不備があれば連絡があるため、申請に使用した印鑑を持って法務局へ出向き対応しましょう。
登記完了証を受け取る際にも申請した時と同じ印鑑が必要です。また、事前に原本還付の申請を行っていればこのときに還付されます。建物滅失登記の完了は、登記事項証明書を取得すると確認可能です。
▼この記事を読んだ人はこんな記事も読んでいます。

建物滅失登記をしなかった場合のデメリット6つ
不動産を解体した際には、建物滅失登記を行わないと、さまざまなデメリットが生じます。
滅失登記は、建物を解体したり、消失してしまった場合に所有者に義務付けられている手続きです。もしも怠った場合は、「登記上建物が存在している」とみなされてしまうのです。
書類の上では、滅失登記が完了するまで古い建物が残っている扱いになります。そのため、資産性の高い更地として売却したり、同じ場所に新しい建物を建設する許可が下りません。
また、固定資産税の金額は登記簿の内容を基にして算定・請求されることから、滅失登記が行われるまでは請求が続いていきます。さらに、元の建物の所有者が亡くなっていると、手続きに必要となる書類が増えることになります。
さらに、滅失登記の申請を怠ることは罰則対象(不動産登記法第164条)ですので、ペナルティとして最高10万円の過料(罰金)が科せられる場合があります。
1:新築の際の建築許可が下りない

解体後の建物滅失登記を怠ると、新築を申請しても更地ではないと判断され、建築許可がおりません。
建物の新築は、事前に市区町村へ建築確認申請を行って審査を受け、許可を得ます。しかし、申請した土地に登記上建物の存在が確認されれば、不備のある建築計画と判断され許可を受けられません。
建物滅失登記の手続きを怠ると、所有する土地を自分の思い通りに使えなくなるということなのです。
2:土地の売却ができない
建物滅失登記をしていない土地は、購入希望者が現れても登記上の土地と現状が異なるため、売却ができません。
更地なら欲しい、という人にとって、登記上建物が残っていると面倒に感じて購入意欲が減退します。たとえ購入しても、新築許可の下りない土地を購入する人はまずいないでしょう。
将来的に利用しない場合や相続物件で売却を望む時は、解体後1カ月以内に建物滅失登記を忘れずに行いましょう。
3:固定資産税と都市計画税がかかり続ける
建物滅失登記を行わない限り、登記簿に課税対象の建物が存在するため、固定資産税と都市計画税がかかり続けます。
固定資産税と都市計画税は1月1日時点の登記を根拠に課税され、固定資産税の評価額を基に都市計画税の課税額も決定します。したがって、適切な滅失手続きを行わないと、課税は継続するため注意が必要です。
ただし、建物を解体して更地にすると、住宅地の特例による軽減税の対象外になり、課税額が増える点にも留意しましょう。
4:法的な罰則に当たるケースもある

解体後1カ月以内の建物滅失登記は、不動産登記法によって規定され、申請を怠った場合には10万円以下の過料の支払いも同様に定められています。
1カ月経過後すぐに過料対象とはなりませんが、速やかに手続きを行っておくに越したことはありません。
※過料とは、民事上の義務違反を指し、秩序を保つために科せられるものです。
出典:不動産登記法|法務省
5:相続手続きが面倒になる
建物の解体が完了した後、滅失登記を放置したまま所有者が亡くなると、相続手続きが速やかにできなくなります。
現状と登記簿が異なると、経緯や事情が明確にできず、相続人に想定外のトラブルが発生します。相続関連の書類をそろえる手間や費用をかけて建物滅失登記を行わなければならず、面倒に感じてそのままになってしまう可能性もあるでしょう。
建物の所有者の責任で、解体は建物滅失登記まで行うことが重要といえます。
6:融資が受けられない場合がある
更地を担保に金融機関から融資を受けようと思っても、登記上建物が存在するため、融資が受けられない事態になります。
現状と登記簿が異なる状況は、金融機関から不備を指摘されます。特に、抵当権の設定された建物であれば、完済していても融資の話は進みません。
建物滅失登記は、現状と登記簿を一致させ、土地を有効活用するために必要な手続きといえるのです。
建物滅失登記は期限内に速やかに行おう

建物滅失登記は、建物を解体したのち1カ月以内に、所有者が登記簿を閉鎖するために法務局に申請する手続きです。
建物滅失登記は土地家屋調査士に依頼できますが、費用負担を軽減するために、自分で行うこともできます。手続きを行わないと過料の対象になり、建物の新築や土地の売却など更地の活用もできません。
所有者が亡くなると手続きも煩雑になるため、建物解体後は、所有者の責任で建物滅失登記を必ず行いましょう。
▼この記事を読んだ人はこんな記事も読んでいます。













